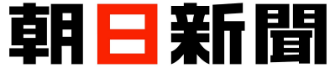自分らしい最期の迎え方
supported by 朝日新聞
肝細胞がんを患っていた夫が息を引き取った。在宅医療を受けながら自宅で過ごしていたため、旅立ちの時には友人らも集まってくれた。また家族で過ごす時間も増えたので、本当に良かったと思っている。ただ、当初は不安な気持ちもあった。
システムエンジニアの夫と2人の子供、そして愛犬を含む家族で都内のマンションに家族で住み、自分たちなりの幸せを築きながら過ごしていた。そんな日々の中、突然、夫のがんが発覚した。病院で抗がん剤治療などを受けていたが、効果が乏しく、病気は肝臓全体に広がり、体力の低下が目立つようになった。主治医からは末期であるとの説明を受けた。
「最期は家で過ごそうと思うんだ」
そして、仕事をしながら過ごしたいという意向を伝えられた。夫の希望を叶えたいと思いつつ、仕事が負担になるのではないかという不安もあった。
主治医にも相談して、在宅医療を受けることになった。がんと診断された時から緩和ケアは受けていたが、自宅で緩和ケアを受けることになり、本当に、最期が近づいていると感じる。
夫のいる生活が戻ってきたことは嬉しかったが、体調も良くないのにパソコンに向かい続けるのを見ているのはつらかった。ここまでして仕事をしなければいけないのか、夫を楽にしてやるのが緩和ケアなのではないか、そんな気持ちだった。
ある日、看護師から声をかけられ、思い切って胸につかえていた気持ちを伝えた。すると、看護師は「緩和ケアは、身体の苦痛をやわらげるだけでなく、その人らしい生き方が少しでもできるようにお手伝いするものでもあるんですよ」と言った。
その場では納得はしたものの、一人で考えているとまた不安になった。そんな時、訪問してきた医師に、声をかけられた。私の気持ちも大切だから、一度家族全員で話をしてみてはどうかという提案だった。夫にこんなことを伝える戸惑いもあったが、話をしてみると、夫の思いも聞けて、息子たちの意見も聞けた。それぞれの不安にケアチームが対応を考えてくれたおかげで不安がなくなり、夫を前向きに支えることができると思えた。
いよいよ仕事も大詰めというある日、夫が私にこんな話をしてくれた。「モノを創っている人は本当に面白いんだよ。そういう人の手助けができる仕事は、やっぱり一番楽しいね」。笑顔で仕事をする夫を、心から応援できるようになって良かった。そして、ついに仕事をやり遂げた3日後、夫は旅立った。
死を想うときにこそ、人は『生』の重みと喜びを実感するのだろう―。
在宅での緩和ケアを始めたころは不安もあったが、家族みんなで納得のできる日々を送ることができた。一緒に過ごした最後の時間は、これからも私たちを支えていってくれる、そんな気がした。
原作:朝日新聞デジタル それぞれの最終楽章
『在宅医療:1 最後の仕事、やり遂げ旅立つ』より
悠翔会理事長(在宅医) 佐々木淳さん